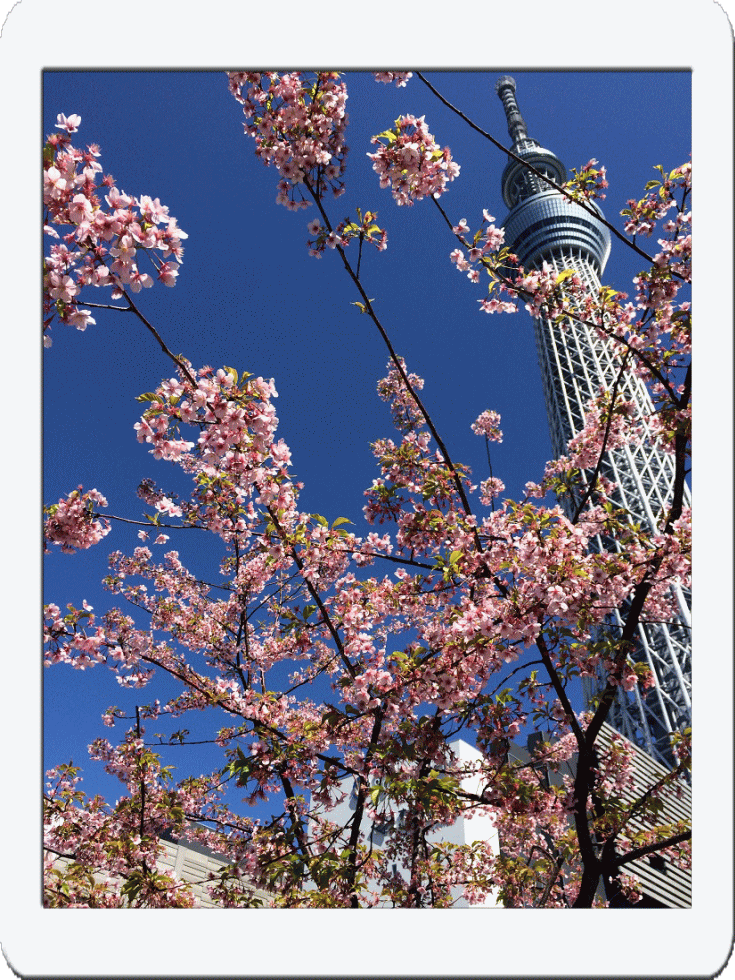 |
失恋W |
桜の季節って人を物悲しくさせるよな。 そんなことを考えながら、俺は某有名スポットでぼうっと立ち尽くし、「独り感傷に浸る男子高校生」に酔ったフリをしていた。というのも、予定では今頃、大好きな先輩に告白して見事想いを果たし、まさにこの場所で最初のデートを始めるつもりでいたから……あぁでも、現実はシビアだ。ナチュラルに落ち込む。調子に乗って告白なんてしなきゃ良かった。地元民のくせにわざわざ買ったこの観光用雑誌も、今は何のアテもなくカバンの奥にしまいこまれているだけだ。 そもそも、先輩は「モノスゴイ」高嶺の花だった。今にして思うと、どこをどう取ったら、両想いになれるだなんて一度でも妄想したのかと我ながら心底不思議だ。 秋川サヨリ先輩は同じテニス部だったから話す機会こそ多かったけど、まさに「こんな女性(ひと)がこの世いるのか」というほどに完璧だった。普通なら到底近寄れないって感じの、何というか「別格」の人。でも、親しみやすくて誰より優しい。ついでに美人で、笑うと可愛い感じもする奇跡の容姿。ベタ惚れだったから多少のフィルターは掛かっているかもしれないけど、それにしても女性ながらに学校を代表する生徒会長で、休日は幼稚園や老人ホームのボランティア活動、極め付けは部活のテニスも全国レベルときては……何を取っても中の中である俺と、逆さにしても釣り合うわけがない。ていうか、普通だったら、告白しようなんて大それたことも思わないだろう。 でもそれをさせたいと思わせる何かが、秋川先輩にはあった。 事実そう思っていたのは俺だけではなく、今年の3月で卒業の先輩に対して、同級生、下級生入り乱れて、皆が一斉に「告白ラッシュ」を開始した。卒業式の日なんて今思うとギャグだ、大袈裟でなく、先輩の前には大行列が出来て、男女関係なく、1人1人が「ごめんなさい、でもありがとう」の連呼をされまくった。あれは最早伝説だ。 まぁそのお陰というかで、俺個人にとっては大きな失恋でも周りにとっては、「玉砕した大勢のうちの1人」として、あまり目立ちはしなかったけど。 先輩は大学へ行ったら、先輩に見合ったカッコイイ彼氏を作るのかなぁ。 (俺はもういいや…現実の女は) 青空をバックに堂々と咲き誇る桜。それらを何となく見上げながら、俺はそんな不毛なことを考えていた。失恋してからは現実逃避に拍車がかかって、これまでは「割と好き」程度だったアニメや漫画にのめりこんでは、可愛い人形が急に動き出して主人公を「ご主人様」と呼んだり、異世界トリップした選ばれし主人公が、エロティックな女戦士と冒険したり。そういうのに傾倒した。そう、だから今だったら、あの桜の木の陰からひょこっと「俺にしか見えない」桜の精なんかが出てきて、俺に絡んできてくれたら最高だと思う。……自分でも少し重症な気がしないでもなかったが、ありえない世界のありえない想像は、傷ついた俺の心を少なからずも慰めてくれるんだ。 だから今日も、ここで暫しの感傷に浸った後は、地元のアニメ専門店へ行って、好きなアニメの新作グッズを買いに行くつもりだった。まぁ、ごくごく一般的な休日というわけだ。 「すみません」 ただ、俺があまりに暇そうだったからか、不意に背後からぽっと声を掛けられた。道を訊かれるのか何かのキャッチか、はたまた宗教関係か。しまったなと思いながら、それでも「はい?」と返事をして振り返ると、そこには見覚えのある顔がにこにこして立っていた。 「あ」 「ああ、やっぱりそうだった! C組の藤九郎(とうくろう)くん! 休みの日に会えるなんて嬉しいなぁ」 「え? は、はぁ…」 俺はこの人を知っているけれど、面と向かって話しかけられたのはこれが初めて。向こうが俺を知っていることこそ驚きだった。相手はうちの学校の新しい生徒会長で、1個上の先輩だ。でも、何の縁もない。唯一接点があるとすれば、俺が3月の告白大会に参加した時、この先輩は生徒会役員の人達と一緒に行列の整理をしていたから、「学園のマドンナに告白した身の程知らずリスト」なんかがあるのなら、チェックを受けているかもしれない。んが、まさか。いくら何でも、そんな事はないだろう。 「何しているの? 誰かと待ち合わせ?」 なのにこの先輩―確か梁川(やながわ)さんという名前だ―は、物凄く愛想の良い笑顔で俺に対してきた。俺は動揺するしかない。もともと人見知りする方だし、何より個人的に生徒会の人達には良い印象を持っていないから。優秀な集団なのは知っているけど、だからこそ、俺が好きだった秋川先輩の第一親衛隊…つまりは、取り巻きみたいな感じで、基本的に俺たち一般人には凄く冷たいという「噂」を散々に聞いていたので。 「あ、もしかして俺のこと知らない? だとしたら馴れ馴れしく話しかけてごめんね?」 俺が緊張で固まったことに恐縮したのだろう、梁川さんは途端苦笑して頭を掻いた。 「あ、違います」 それで俺もたちまち焦って首を振った。無駄に「すみません」ともう一度謝ってから、どこの不審者だというくらいの怪しさで視線を動かしながら弁解した。 「学校の生徒会長さんだから、勿論知っています。梁川先輩ですよね」 「あ、良かった。うん、そう! 梁川唯史(ただし)。君は、2年の藤本藤九郎くん」 「は…はい、そうです」 「俺が君のことを知っていて驚いたみたいだけど、俺たちの間では、藤九郎君は結構な有名人だよ。先月の卒業式で、秋川先輩に告白する会に参加していたでしょ?」 「………はい」 そのまさかだった。生徒会の人達は、憧れの秋川先輩に告白した不届き者リストを本当に作成していたのだ。でなけりゃ、俺のフルネームまでばっちり覚えているわけがない。何だろう、制裁でもされるんだろうか。フラれた上に、残りの高校生活でこんな人に目をつけられたら最悪だ。 でも俺は秋川先輩のことはもうすっぱり諦めているし、これからは二次元の世界へ旅立とうと思っているのに。 「俺の中では、君の告白が1番良かったね。最高だった」 「え?」 ところが、俺が悶々と嫌な想像ばかりしていたところへ、梁川先輩は突然そんな風に言って俺を誉めた。驚いて思わず顔を上げると、相変わらずニコニコとした笑顔で、梁川先輩は俺のことを見下ろしていた。俺は秋川先輩より背が低いことがコンプレックスだったけど、この先輩なら、長身の秋川先輩ともよく釣り合うだろう。 「本当だよ? 他の人は、何ていうかノリでやっているところがあったけど、藤九郎くんの告白は、秋川先輩への本気度って言うの? そういうのが凄く伝わったしさ」 「あ、ありがとうございます。でも、結局フラれちゃいましたけど」 はははと間の抜けた笑いを浮かべながら、俺は本気で照れた。だからもう一度俯いて自分の足元を見た。 確かに、あの時の俺は他の誰よりも本気だった自信はあった。だって本当に心から先輩のことが好きだったんだ。絶対望みがないのは分かっていたけど、このままただの「可愛い後輩」でさよならするのは耐えられないくらいには、ホントに、一人勝手に盛り上がっていた。…まぁフラれた今は、可愛い後輩と思われていたのかすら自信がなくなっているけども。 「いやでも、あの人も見る目がないよね。俺だったら、藤九郎くんみたいな子が告白してくれたら、絶対一発OKするのに」 「……は?」 「俺と付き合わない? 俺じゃダメかな?」 「え……えーと……」 何だ、この人。一体いきなり何を言い出すんだ。たぶん冗談なんだろうけど。だって笑っているし。 でも、目は笑っていない。え、本気?真面目?いや。いやいやいや、でも。そんなことはないだろう、いきなり。そうだ、いきなりすぎる。何を突然訳の分からないことを言い出しているんだろう。 「ちょっと…その、言われた意味がよく分からないんですが」 だから正直にそう返すと、梁川先輩は「まぁそうだろうね」と至極冷静に応えた後、いかにも置きやすいというように俺の頭に片手をもっていってぽんぽんとやった。 「でも、ここで偶然会ったのも何かの運命かなあなんて思っちゃったから。本当はもっと段取りを踏んでから告白するつもりだったんだけど、ついね。でも本当に本気なんだよ。俺、藤九郎くんのことが好きなんだ。だから、俺と付き合ってくれませんか?」 「いやぁ……それは……ちょっと……」 「駄目?」 「は、はい…すみません。俺…ちょっと、その、そういう趣味はなくて…すみません」 「俺が男だからダメ? 俺っていう人間そのものがダメ?」 ぐぐいと顔を近づけて、梁川先輩は尚もしつこく訊いてきた。何だかコワイ。でも、先輩の人間性がダメってことはない。だって先輩のことは何も知らないし。確かに「生徒会の怖い人」ってイメージはあるから、最初から良い印象はないけど、俺の決死の告白を誉めてくれたし、今はそういう悪印象も薄らいでいる。 そう、だから、先輩が「男」だということがまずもって「ダメ」なんだと思う。 「そうなんだ。良かった」 すると俺の正直なその想いに、梁川先輩は心底嬉しそうに微笑んだ。 ただ、話はそれで終わりじゃなかった。 「それなら俺にもまだ望みはあるね。そういうのは、後からどうとでもなる問題だと思うよ。藤九郎くんの中の常識を変えちゃえばいい。俺を知ってもらって、今ある君のありえなさなんてどうでもいいって思えるくらいにしちゃえばいいんだから」 「いや、でも」 梁川先輩を知る為には、これからもいろいろ関わりを持つということになるんじゃないだろうか。部活も違うし、学年も違う。それ以外でも、「何か」が根本的に違う。そう、住む世界が違うのだ。そういう感じなんだよな、あの生徒会の人達って。……その中で秋川先輩だけが「下界に降り立った天使」みたいな感じで、俺たちにも近寄りやすい印象をくれる別格だったんだけど。 でも何だか凄く強引な梁川先輩の押しに断れ切れなくて、俺は結局先輩とアドレスの交換をしてしまった。そしてその日は、アニメ専門店へ行くとも言い出せず、梁川先輩に引きずられるままに、秋川先輩と辿るはずだったお決まりデートスポットを巡る羽目になってしまった。またそれ以降、先輩はやたらと学校でも俺に話しかけたり、マメにメールや電話をしてきたりして、傍から見たら異常とも言える「猛烈アタック」をしてきたのだ。 ただ、そんな日々がひと月くらい続いた頃。 俺が梁川先輩のことを「ちょっと分かってきたかも」なんて思い始めていた頃に、その「事件」は起きた。 事件、なんて大袈裟だろうか。でも、事件かな。結論から言うと、俺は、生徒会の人達が梁川先輩の俺への猛烈アタックは「悪意あるゲーム」と話しているのを偶然にも立ち聞きしてしまった。 しかも。 梁川先輩は、秋川先輩の恋人だった。 「梁川は、あのキモオタ野郎をいつまで構うつもりなのかね?」 それは放課後の、生徒の数もまばらになり始めた時間のことだ。 「あいつが言うには、今やっと“いい人”くらいにまで昇格してきから、もうちょいかかるってさ」 そういう密談は周囲に気を配ってやるべきなのに、生徒会の人達は不用意にも3年の教室で堂々と「梁川先輩が俺をはめる話」で盛り上がっていた。 「彼女にちょっかい出されてむかついたんなら、もっと直接的に痛めつけるなり脅しかけるなりすればいいのに。あいつってやる事がいちいち陰険だよな」 「唯史もお前にだけは言われたくないだろうけどなー。陰険さなら同レベルだろ? お前には単に辛抱が足りないだけ」 「何の辛抱だよ。好きでもない奴を好きにさせるまで辛抱するとか、俺にはありえん。めんどい」 「でもさ、梁川があそこまでするのって、やっぱり嫉妬心ってやつだよな? そういうの結構意外だったから新鮮だよ。これまでは秋川ちゃんのことも、そこまで好きって風には見えなかったから」 「それは言える。あいつら昔馴染みだし、何より2人とも性格が淡泊過ぎるから、付き合っているってのも全然知られてないし。だからこそ、あんな告白大会も起きたわけだし」 「あれは秋川先輩も最悪だったよなぁ。完全に楽しんでたもん」 先輩方の嘲った声は氷のように冷たかった。不思議。だって、ただの声に温度を感じるんだから。 でも、つまりそうなのかあ、と。 俺は妙に納得しながら、その場を離れた。カバンの中には梁川先輩から借りた、好きアニメの設定資料集がズシンと大きく幅を取っている。俺の熱弁を聞いて「俺もはまっちゃったから」なんて言いながら貸してくれたけど、あれも全部演技だったのかなぁ。彼女に懸想した男に復讐する為そこまでやるとは、金持ちでないと出来ない所業だ。だってわざわざ嫌いな奴の為に話を合わせて、散財までするなんて、俺には考えられない。 けど確かに、梁川先輩のそういう「辛抱」によって、俺は先輩のことを「いい人」だと思い始めていた。いや、もう完全にそう思っていた。最初にあった悪い印象なんて完璧に消えていたし、多少強引だなとか、スゴイマイペースだなとか思うところはあっても、純粋に、「いい人」だなって。 それに、例え同じ男でも、あれだけ「好きだ」、「付き合って」と繰り返されれば失恋した身には染みわたるし、そもそも俺は誰かにあそこまで好意を表現されたことがなかったから。もしかして、このままいったら本当に先輩のことを好きになるかも…そんな、本来なら全く無縁だったアブノーマルな世界のことさえ、最近ではちらっと妄想していたくらいだ。本当にちらっとだけど。 でも、そうなのか。そうだったのか。 梁川先輩は秋川先輩の彼氏で、だから彼女の周囲をうろちょろしていた俺を、前から気に食わないと思っていたのか。おまけに、恐らく俺は先輩にとって「1番」むかつく告白をした。だから余計癇に障ったに違いない。それでこういう、ちょっとしたお遊びを開始したってわけだ。俺はおたくだから知っている、こういう風に好きでもない奴に好きだと言って、相手が本気になった途端「全部嘘でした〜本気にしたの?バカじゃない?」と相手を地獄に叩き落とすパターン。可哀想な主人公がよくやられるいじめの一つとして、すでに似たような創作がたくさんある。だから俺には耐性があるのだ。 「そう、だから……こんなん分かっても、全然ダメージなんかないんだからな。ざまあみろ」 ぶつぶつと呟きながら、俺は負け惜しみも良いところな台詞を叩き落として歩き続けた。どこへ向かっているのかもよく分からないけど。とりあえず学校は出たいな。梁川先輩、もといあの生徒会の人達からは少しでも遠い所へ行きたいから。はあ、それにしても本当に最悪だ。少し考えれば分かることだったのに。当たり前だ、あの人が俺を好きになるなんてあるわけがないんだ。何を勘違いして、あの人のにこやかな笑顔に安心して、好きなアニメの話なんてしてしまったのだろう。心を許すにも程がある。 恥ずかしい。 「うわっ…!?」 その時、突然制服に入れていた携帯がブルルと震えて、俺は思い切りびくついて声を出した。慌ててそれを取り出すと、すでに何回かの着信があって、今届いたメールには送信主「梁川先輩」で、「今日部活ないんでしょ?一緒に帰ろう」と言うメッセージが入っていた。 「いや、帰るわけないし、二度と話したくないし」 俺はそう思いながらすぐさまこのアドレスを着信拒否に設定しようとして、しかしはたと思い留まった。 いいんだろうか、それで。と、咄嗟に思ったのだ。 アニメの設定集を借りっぱなしだから…とか、そんな理由では断じてない。それは人としてきちんと返すとして。まがりなりにも、失恋してからこの一か月、俺は確かにちょっとだけ楽しかった。あの人は俺を忌々しく思いながら付き合っていたんだろうけど、俺はそれを全然感じなかったし、もしかしたら好きになれるかも、なんて考えてすらいたのだ。これってスゴイことだ。先輩は詐欺師の才能がある。それってはっきり言って最低だ。ただ、その最低な人は俺が大好きだった秋川先輩の彼氏なわけで、最低は最低なりに、秋川先輩を好きだからこそ始めてしまった「過ち」だ。人を傷つけようとしてこんな遊びを始めたんだから酷いことには変わりないが、幸い俺は打撃を与えられる前に気づくことが出来たんだから、梁川先輩には、「確かに俺も彼女さんに身の程知らずな告白をして悪かったけど、いくらなんでも先輩の悪戯はあんまりだから、今度から気をつけた方がいいですよ」くらい言ってあげた方がいい気がする。 「いや待て…。でも、そんな親切、わざわざしてあげる必要あるかな? ないよな。あるわけない。それに先輩は俺が大嫌いなわけで、そんな奴の忠告聞くわけがない」 言いながら俺はぐしゃぐしゃと髪の毛をかきむしった。ついでに自然に目から出てきた水もごしごしと拭い取る。何だ、先輩は「もうちょっとかかる」なんて言ったみたいだけど、そんな必要ないじゃないか。だって俺はまんまとショックを受けている。先輩に騙された。先輩が俺を好きだと言ったのは嘘だった。それどころか、梁川先輩は秋川先輩の彼氏で、秋川先輩を好きだった俺を憎んですらいた。 「藤九郎!」 ヤバい、立ち止まっている場合ではなかった。 俺の背中にかかったその声に、俺は思わず身体が跳ね上がるほどに驚いてしまった。振り返らずとも分かる、その底抜けに明るく綺麗な声は梁川先輩のものだ。思えば先輩は、俺に対してはいつもあの生徒会の人達が話していた時のような「ブラック」な気配は微塵も感じさせない。先輩はいつだって完璧な態度で俺に接していた。 その先輩が俺にどんどん近づいてくる。 「良かった、まだ帰ってなくて! メール見た? 藤九郎のところ、今日部活ないって部長さんから聞いたから、慌てて連絡したんだよ。さっき電話もしたんだけど、気づかなかった?」 「俺…電話、あんまり好きじゃないから、音消してて」 「そうだよね、うん、分かってる。だからメールで……って、どうした!?」 先輩は俺の顔を見るなり仰天したような声を上げた。涙を拭いても、泣いていたのは余裕で分かるんだろうな。鏡がなくてもよく分かる。今きっと俺は凄く酷い顔をしている。梁川先輩をまともに見られない。 「どうした、何かあった!? 何か……誰かに何か……」 うん、酷いいじめをうけた。目の前のあなたに。 でも、何か言わなきゃと思うのに何も言えない。あ、そうだ、借りた資料集を返さないと。もう今日を限りに先輩とは二度と話すことはないんだし、後腐れなくしておく必要がある。 なのに、腕が重くて、カバンを開けるのが凄く億劫。 先輩と一緒にいるのが嫌だ。 「ちょっとこっちおいで。ここ座って。どうしたの、何かあったんだろ、言ってみな?」 そうとも知らず、先輩は優しく俺の肩を抱いて校庭の隅のベンチへ連れて行き、俺をそこへ座らせた。俺も成されるがままだ。本当は早く逃げ出したいのに。ダメだ、肩を掴まれた先がただじんじんとして何も言えない。文句の一つも言わなきゃなのに。いや、謝るのが先かな?だって確かに、彼氏にしてみたら、昨年から今年3月までの俺ってひどかったもん。「もしかして両想いになれるかも」なんて勘違いするほどには、秋川先輩にしつこく絡みまくっていたし。 だって、梁川先輩みたいな彼氏がいるなんて知らなかったから。 「せ…先輩がむかつくのも分かります…」 だからやっとそれだけ言った。 「え?」 当然のことながら先輩はそれにきょとんとした反応を返した。俺はもうただ言うしかないと思って、膝に置いたカバンの上で両拳をぎゅっと握りしめた。 「そりゃ腹も立ちますよね。あんな完璧な彼女に、こんなキモオタがストーカー混じりにまとわりついていたら。うん、はい。俺も、今だから客観的にあの時の俺を見つめ返せますけど、有り得ないですもん、普通に考えて。俺みたいな奴に望みがあるわけなかったのに。妄想力だけは著しいんで。昔から」 「ちょっと待って、何の話をしているの? もっと分かるように――」 「だからつまり、先輩の彼女である秋川先輩に告白した身の程知らずな後輩がいて、それはつまり俺のことですけど、それにむかついた梁川先輩が俺をはめようとしたって話です。もともとノーマルな俺を男好きにさせた挙句、最後には崖から突き落とすってすごいシチュエーションですよね。アニメとかでもよく見る設定ではありますけど。でも何ていうか、先輩って前から思っていましたけど、Sっ気が強いと言うか。あ、でも、むかつくのも仕方ないと思うので、それはホントにすみませんでした」 酷い目に遭って笑い者にされているのは俺なのに、何で俺が謝っているんだ。 ――と、もう1人の俺が冷静にツッコミを入れていたけど、もう1人の意識に上がっている俺はごく自然にするっと謝罪の言葉を紡いでいた。気も弱いのかもしれない、素の俺は。そうだ、俺は梁川先輩を好きだけど、ちょっと怖いとも思っていて。だからビビっているのかもしれない、こんな手の込んだ嫌がらせをする先輩に、これ以上つきまとわれて、さらにどんな酷い仕打ちをされるのかと、恐れているから下手に出ているのかも。 「藤九郎」 だって先輩は、俺にはいつもこういう優しい声しか出さない。それでいて根っこでは俺を「キモオタ野郎」と思っていたと言うのだから、これを恐ろしいという言葉以外で表現しろというのは、それこそ無茶じゃないだろうか。 「藤九郎、こっち見て。ねえ、こっち」 「……ちゃ、ちゃんと見て、その上で、『やっと気づいたかよ、キモオタ野郎』ってほくそ笑む先輩の顔を見たら、このゲームはちゃんと終わりますか?」 「……………」 震える声で必死に発した俺の質問に、すぐの返答はなかった。途中でバレたことに悔しい想いをしているのか、多少はしまったと思っているのか。後者なら良かったけど、前者だったら嫌だな、怖いな、と、思っていたら。 「ひっ…」 いきなりがつりと髪の毛を掴まれて、俺は無理に顔を上げさせられた。い、痛い。髪の毛抜ける。そして怖い。先輩は怒っているんだと思った。 その先輩がきっぱりと言った。 「藤九郎のこと、キモオタ野郎なんて思ってないよ」 「で、でも怒ってる……」 「はっ……怒ってないよ。むしろ怒る権利を持っているのは藤九郎だよね。サヨリと付き合っていたこと、内緒にしていたんだから。誰に聞いたの?」 「だ、誰って言うより…さっき、3年の教室で、生徒会の人達が話しているのを聞いて」 「ああ、そうなの。あいつらがどういう話し方していたかは想像がつくよ。……そう、だから藤九郎は俺を見てくれないんだ? ねえ、見て? 俺の顔」 確かに俺は、顔を上げさせられても尚頑なに目を瞑っていた。先輩のことを直視するのが怖かったから。 でも先輩は俺にきちんと見ろと言う。 「み、見たらこのゲームは」 「終わるか終らないかって質問には答えられない。その質問自体が的外れだから。でも、これだけは言えるのは、見てくれないと、ここから先へは一歩も進めないよ。永遠にこのままだよ」 「永遠にここで髪掴まれたままなんですか…」 「そうだね。俺はそれでも全然構わない」 「禿げちゃいます…」 「大丈夫、藤九郎が禿げちゃっても俺は愛せるから」 冗談なんだか本気なんだか分からない言葉に俺は思わずカッとした。だって先輩はやっぱり酷いと思ったから。 「こんなの、時間の無駄です…っ。生徒会の人達が、先輩は辛抱強いって。俺もそう思う、嫌いな奴をはめるのにこんな時間かけて、ふ、不毛としか言いようがない。『俺の女に近づくな』って、一言でも言ってくれれば、俺だって……諦めたのに!」 「……そうかな」 「……え?」 「それは違うと思う」 確信めいた風に言って、梁川先輩は俺の頬をさらりと撫でた。俺はそれに露骨にびくっとしてしまい、凄く恥ずかしくなった。 でも先輩は構わず、さらに俺の顔を撫でながら言うんだ。 「藤九郎はあそこでサヨリにきちんと告白して、フラれたから良かったんだよ。あれをしたから、きっぱりサヨリとさよならできた」 「…………」 「誰に何を言われても、藤九郎は自分が好きだと思った人のことはずっと一途に好きでいられる子だよ。その上、自分の気持ちにきちんとケリもつけられるんだから、藤九郎は本当に凄いし、偉いと思うね。そういうところを見ていたから、ずっと気になっていて、極めつけはあの卒業式の告白だ。あれで俺も、あぁ本当にいいなって。藤九郎のこと好きだなって。あの想いが俺に向けられたらって、サヨリに嫉妬したよ。ねえ、お願いだから、目を開けてくれないかな。あいつらが俺の言動をどう解釈しようと、俺の藤九郎への気持ちは本物だよ」 梁川先輩は元から饒舌な人だ。嘘がバレても冷静に対処するなんてお手の物だと思う。だから俺は、このセリフが本当なのか嘘なのかを見極められる自信がなかった。先輩は目を見れば分かると言いたいんだろうけど、俺自身は、恐らく先輩の顔を見ても確信を持ってこうだとは言い切れないだろうなと「分かって」いた。 でも目を開けなければ先へは進めないと言う。だから仕方なく、俺はそろりと目を開けた。 そして先輩の真剣な顔を見て、やっぱり、見ても分からないじゃないかって思った。 「本気だって言われても、それを本当って思えないです」 だから俺は正直に告げた。 「ずっと良くしてくれた先輩と、話したこともない生徒会の人達の噂話とどっちを信じるんだって言われたら、それは先輩を信じたいけど……信じた途端、さっきの人達が出てきて、『やっぱり引っかかった!』って。そんな風に皆で俺のことを笑ってきたらどうしようって、思っちゃって…ちっちゃい奴だと思うかもしれないですけど、そういうのを考えちゃうんです。だから…すみ、すみません」 「あの時……初めて俺が藤九郎に声をかけた時、あそこで俺は、俺のことを知って欲しいって言ったよね。藤九郎は、俺が連中とそういうことする人間に見えるの」 先輩の声は沈んでいた。俺はそれに胸が痛んだけど、嘘をついてごまかすわけにもいかない。今の本音を言うしかなかった。 「思いたくはないんです。ホントに。でも…少なくとも、先輩が秋川先輩の彼氏さんなのは、間違いないんでしょ?」 「……この状態で、もうとっくに別れているって言っても、信じないよね」 先輩が深くため息をついてそう言った。それからようやく俺から手を放してくれて、悪かったとでもいう風に、さっき酷くした髪の毛を優しく撫でつけてくれた。 俺はそれでちょっとだけ落ち着けて、だから、やっと動かせた手で、カバンの中からあの設定資料集を取り出した。 「これ、凄く面白かったです。ありがとうございました」 「あげるよ」 「そっ…貰えないです」 「藤九郎が要らないなら捨てるしかない。これは本当に嘘ついていたけど、そのアニメ、正直どこが面白いのか、俺には分からなかったから。ごめんね」 「……そうなんですか」 「好きな子の好きな物を、一緒に好きって言いたかっただけだから」 「……秋川先輩とやればいいのに」 俺がついぼそりと僻みめいたことを言うと、先輩は初めて見たってくらいに、凄く嫌そうな顔をした。 「あのね、藤九郎はサヨリのこと、本当にはよく分かっていなかったと思うよ。優しくて綺麗な、完璧な先輩って思っていたかもしれないけど。惚れたが故の幻想ってやつ? 腐れ縁だし、似た者同士だからこそ言えることだけど、あいつって基本無趣味だし、面白味のない女だよ。人としての熱がないんだ」 「熱?」 「情熱って言うのかな。愛情って言ってもいい。藤九郎が普通に持っているもの。そういうのが、あいつにはないの」 「じゃあ…その秋川先輩と同じだって言う、梁川先輩も…?」 恐る恐る訊ねると、先輩はどこか決まり悪いそうに眉をひそめた後、やがて寂しそうに唇を上げて笑った。 「ここ一か月は凄く熱くなれたけどね。本当に、最高に楽しかったから。藤九郎と仲良く出来て」 「…………」 「もう俺たち、仲良く出来ない? 俺に望みはないの?」 「………ごめんなさい。俺、もう行きます」 このままここにいたら流される。そんな危機感があって、俺は急いで立ち上がった。酷い俺はまだその可能性を捨てきれていなかった。先輩の仲間である生徒会の人達があの木の陰にいて、今にも「先輩のこと怒っていないです、これからも仲良くしたいです」と言い出す俺をわくわくしながら待っている、そんな可能性を。 そして大好きな梁川先輩は意地悪く笑って、「俺は君のこと好きでも何でもないから」って言ってくる。 そんな風になるくらいなら、うやむやのまま去りたい。 こんな俺の、どこが「きちんとけじめをつけられる凄い偉い人」なんだろう? 「ごめんなさい」 だから俺はもう一度ぺこりと頭を下げて謝ったんだけど……。 「……藤九郎」 先輩はそれには応えず、ただ俺の名を呼び、俺の首をいきなり掴むと、無理やり引き寄せてキスをした。 先輩は俺の唇に自分の口をくっつけたのだ。 「ひっ…な…!」 俺にはファーストキスなのに、こんなのあんまりだ。 「なん、何、せんぱ…っ!」 「怒っていいよ」 動揺しまくる俺とは対照的過ぎるくぐもった声がぽつりとそう言った。俺は初めて先輩の顔を直視した。綺麗な顔だけど、どこか仄暗くて恐ろしい。一度目をつけられたらとんでもないことが起きそうだという予感は間違いのないものだという気がした。 それでも俺は繰り返すしかないけれど。 「ごめんなさい!」 先輩の返答は待たず、ただもうダッシュだ。キスに狼狽えるみっともない俺の図があったのに、あの木陰から生徒会の人達はやって来なかったけど。今はそんなこと、どうでもいい。俺はただもう先輩から逃げた。 無理だ、という想いと。 絶対無理だ、という想い。 その単語をひたすら思い浮かべながら、俺は心臓が破けるんじゃないかというくらいに無理やり走り続けた。 そう、だってそうすれば理由が出来る。この心臓がばくばくしているのは、走っているせいなんだって。秋川先輩に告白した時より胸が苦しいなんて、そんなのも嘘だって。夜にはこの鼓動の速さもおさまっている。そして明日からは、これまでの日々にさよならをして、また二次元の世界へ戻るのだ。 「はぁ…明日は…はぁ、アニメイトへ、行こっ…!」 そして先輩に突き返したあの設定資料集を購入する。――好きな物なら借りずに買え。おたくの鉄則を何度も繰り返しながら、俺は明日の筋肉痛を考慮せずに駅まで一度も立ち止まらなかった。 |
|
戻る |